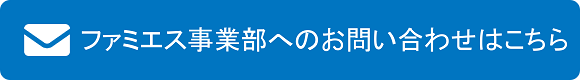インテリア・収納術
2024年12月17日 公開
Q.鏡餅や門松はいつ飾って、いつ片付ければいいのでしょうか?
地域によって違いはありますが、一般的な時期をご紹介します。
街中では大きなクリスマスツリーやリース、色鮮やかな電飾などが寒い季節に彩りを加えていますね。ツリーやリースは片付けるタイミングがわかりやすいかと思いますが、お正月飾りはいつまで出しておくものなのかご存じでしょうか?
スーパーなどで売られている光景はよく目にしますが、クリスマスなどに比べると飾る期間についてはあまり知られていません。
そこで今回は、お正月飾りについて、いつ飾りいつ片付けるべきなのかをご紹介します。
そもそも「お正月飾り」って?

お正月とは本来、その年の豊穣を司る歳神様をお迎えする行事です。
お正月は1月の別名でもありますが、3日までを「三が日」、7日(関西の一部地域では15日)までを「松の内」と呼び、特にこの期間を「お正月」とすることが多いようです。
一般的にいわれていることですが、日本の神様は送り迎えを必要とします。家の外や玄関に門松や注連飾りを飾るのも、そこが清浄な場所であることを示し、歳神様が家に訪れる際の「依り代(よりしろ)」(目印)とするためです。お盆の「迎え火」にも同じ意味が込められています。
そして、お正月飾りの代表格といえば、やっぱり「門松」「注連飾り」「鏡餅」ですね。そこでこの三品について、準備から片付けまでの時期や方法を、ちょっとした知識も交えながらご紹介します。
お正月飾りはいつ準備するの?
お正月飾りの準備は12月28日までに済ませましょう。29日は「二重苦」と呼ばれたり、「九」が「苦」に通じることから、「苦しみを招き入れる日」として嫌われています。また、31日も、お葬式が一般的に「一夜飾り」になることや、「年末ぎりぎりに神様を迎える準備をするのは誠意不足」という考えから避けられています。そして29日と31日の間にあたる30日も良い日取りとはされていません。
というわけで、お正月飾りの準備は28日までに済ませ、心に余裕をもって歳神様をお迎えしましょう。
お正月飾りの飾り方
門松

松は神様の依り代と信じられ、玄関前に飾る風習ができたといわれています。
松は「待つ」にもつながり、竹は冬でも色濃くまっすぐに伸びる節があるので、門松にはけじめの意も込められています。
飾りの特徴
松を中心に据え、3本または5本、7本の葉つきの竹を添え、すそに松の割り薪を並べて荒縄で3箇所を三巻き、五巻き、七巻きと、節目を見せて七五三に結んだものが正式な門松とされています。
最近ではデザインや置き場所に配慮されたものや、ミニ門松の手作りキットなども販売されています。
注連飾り

神社が注連縄を張り巡らせるのと同じ理由で、自分の家が歳神様をお迎えするのにふさわしい神聖な場所であることを示すために始まったとされています。
つまり、注連飾りが飾られている家には、歳神様が安心して降りてきてくださる、というわけなのです。
飾りの特徴
注連縄に裏白(清廉潔白を表す)、だいだい(家が代々繁栄する)、ゆずり葉(家督を譲って家系を絶やさない)などの縁起物を飾りつけたもので、玄関先や神棚に飾ります。
門松と同様、最近はモダンなタイプも多く出回っており、また、おしゃれな注連飾りを手作りされる方も少なくありません。お好きなもので構いませんが、ワラを使った注連縄を用いるのが良いでしょう。
鏡餅

丸い形が昔の鏡に似ているところから名付けられたとされています。鏡はもともと金属の円盤で神聖なものとされ、魔除けの力もあると信じられてきました。
また、「三種の神器」のひとつで、天皇家で代々受け継がれているように、日本人にとっては宝物の象徴でもあります。飾る場所は玄関や床の間です。
飾りの特徴
三方(神事に使われる台)に奉書紙を敷き、左右に裏白またはゆすり葉を配します。そのうえに大小2個の丸餅をのせ、だいだい(みかんでも可)や伊勢えびなどの縁起物を飾ります。ちなみに三方が用意できない場合は、四角いお盆を使用しても良いでしょう。
これは、お餅が「丸=陽の気」を持っているため、「四角=陰の気」のお盆にのせることで気を「中庸」とするためです。
いつまで飾る?後片付けの方法は?
【門松・注連飾り】「どんど焼き」に持って行きましょう

門松・注連飾り・鏡餅のいずれも松の内(一般的には1月7日)まで飾っておきますが、鏡餅だけは「鏡開き」が行われる11日まで飾っておいても良いとされてるところが多いようです。
松の内が終わって取り外した門松や注連飾りは、神社などの「どんど焼き」(お正月飾りを燃やす行事)に持ち寄り、お焚き上げをしていただくのが本来のかたちです。清浄な火でお正月飾りをお焚き上げし、歳神様はその煙に乗って天にお帰りになると考えられています。このどんど焼きは「小正月」にあたる1月15日に行われるのが一般的ですが、会場の都合で日程がずれる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
また、どんど焼きに持っていけない場合は、次の方法で処理してください。
まず、新聞紙や半紙などの大きめの紙の上にお正月飾りを置きます。次に、塩を「左・右・中央」にかけてお清めをし、そのまま包みます。そして、一般のゴミとは別の袋に入れて搬出します。その際は忘れずに歳神様への感謝の思いを込めるようにしましょう。
【鏡餅】「鏡開き」をしていただきましょう

1月11日は「鏡開き」です。お正月に歳神様にお供えした鏡餅を下げて、無病息災を祈りながらお汁粉やお雑煮などにしていただきます。
鏡開きを行う際は、刃物を使うと切腹や戦いを連想させることから、手や木槌を用います。また、「切る」「割る」という言葉は避け、末広がりを意味する「開く」と表現します。「開く」という言葉には、新しい年がいよいよ本格的に始動するという意も込められているそうです。